社会と共に変化する不動産マーケットのいま、そしてこれから。
今後どうなっていくのか?世の中の様々な動きから不動産市場を読み解く。
3年後に迫る東京五輪へ向けた取り組み、昨今の金融政策や税制の動向、そして都心部への人口流入や空き家の増加。こうした社会の動きは、不動産市場にも様々なかたちで影響を及ぼしています。絶えず変化し続ける不動産市場の中で、確かな資産経営の方向性を見極めるためには、マーケット全体のトレンドや今後の見通しについても、きちんと把握しておきたいものです。
そこで今回は、長年にわたり首都圏や大都市の不動産市場を観測・分析してきたニッセイ基礎研究所の竹内一雅氏に、特に東京における不動産市場の現在の状況や、これから東京五輪が開催される2020年までの中期的な展望についてお話を伺いました。
投資も人口もさらに拡大し続ける
東京の不動産市場を取り巻く状況
1990年代後半から東京など大都市圏のオフィスを中心に不動産市場を見てきた経験からも、現在の東京の不動産市況は概ね好調に推移していると感じています。この状況を後押ししている要因として挙げられるのが、政府・日銀による昨今の低金利・マイナス金利政策と円安、そして2015年からの相続増税です。
金利が下がって借りやすくなったお金が不動産投資として市場に流れ込み、円安で海外からの投資も増加した結果、不動産価格は上昇を続けてきました。一方、住宅着工戸数は2016年の5月から7月にかけて年率換算で100万戸を超えました。この大きく増加する住宅着工数は、低金利などに加え、相続税対策として急増したアパートなど、賃貸住宅の新規建設により下支えされています。
また、人口動態も東京の不動産市場に大きな影響を与えています。ご承知のとおり、日本は出生率低下などの影響で2010年頃をピークに人口減少局面に突入しました。しかし一方で、大都市圏、特に東京圏では地方からの転入超過による人口増加が続いています。転入超過は特に大都市の中心部で顕著に見られ、東京都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)では人口が最も少なかった1997年に比べて、2014年時点で3割以上も増加しています(グラフ①参照)。
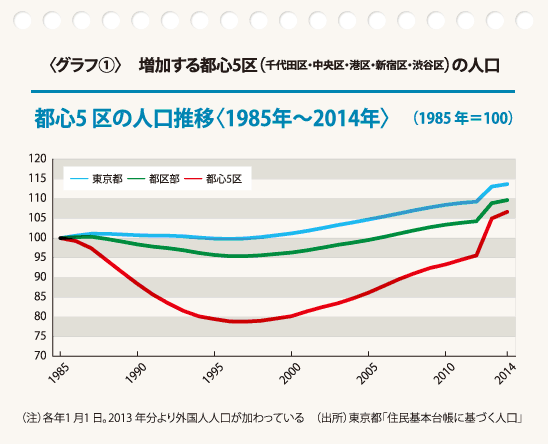
東京を含めた主要都市の中心部ではオフィス需要よりマンション需要が拡大するという見通しに基づく、マンション開発の進展も、転入超過数の増加に拍車をかけています。こうした「都市のコンパクト化」が進む一方で、日本全体では今後、年間で50万人、100万人と人口が減少していくわけですが、地域間で大きく異なる人口動態は、そのエリアの不動産市場、特に需要に対して強い影響力を持つようになるでしょう。
そして、今後の不動産市場を考えるうえで重要な意味を持つのが、東京五輪が開催される2020年です。それまでに様々な日本の課題を解決する必要があり、私たちはこれを「締切効果」と呼びます。各種インフラ整備の進展が予想され、景気も基本的に安定的に推移していくはずです。なお、2019年10月には、税率8%から10%へ消費増税が予定されていますが、このタイミングでの増税は翌年の東京五輪開催の恩恵で、駆け込み需要の反動減による極端な消費の減少は回避できる可能性があります。
都心部の賃貸住宅需要は底堅く、
高騰した建築費はピークアウト
では、具体的に現在から2020年にかけて、東京の不動産市場がどのように推移していくのか、統計などをもとに考察していきたいと思います。
まずオフィス市場ですが、2018年から2020年にかけて東京ではオフィスの大量供給が計画されており、小さな調整局面が入ると思われます。全体の景況としては決して悪くはないのですが、オフィス市場はほぼ横ばいで推移していくことが予想されます。
次に分譲マンション市場については、2016年6月まで、いわゆる“億ション”と呼ばれるような高額物件が特に高い契約率を達成していました。マンションの価格帯と契約率の関係をグラフで表すと、低価格帯と高価格帯が低く、中価格帯のボリュームが厚い「逆U字型」になることが多いのですが、当時はこれが逆転して、低価格帯と高価格帯の契約率が高い「U字型」になっていたのです。この特殊な状況は、価格と相続税・固定資産税評価額との差分に着目した、いわゆる「タワマン節税」がその一因でした。しかし、2016年後半からはマンション価格上昇の一服感から高額物件の契約率も鈍化の傾向が見え始め、米国を含めた世界経済の不安定要素の影響もあり、現在は見定めの期間に入っている状況です。
価格高騰から、分譲住宅の購入検討者が賃貸住宅に流入・滞留する状況は、賃貸ニーズの下支えになっているようです。ただし、前述のとおり賃貸物件の供給自体も多いため、空室が生じたり賃料が下落しているエリア・物件もあるなど、優勝劣敗の様相は変わらない傾向にあります。
なお、東日本大震災以来、建設労働者不足などを理由に建設工事費が高騰していましたが、これに関してはすでにピークを打ちました(グラフ②参照)。その1つの要因は、最近の円安傾向などの影響もあって資材費や原燃料費が圧縮傾向となっているためです。一方、肝心の労働者不足に関しては、その解消のために賃金を上げて人材を確保している状況があります。つまり、賃金アップで人手不足はほぼ解消されており、これ以上人件費を上げていかなくても済むようになってきということです。
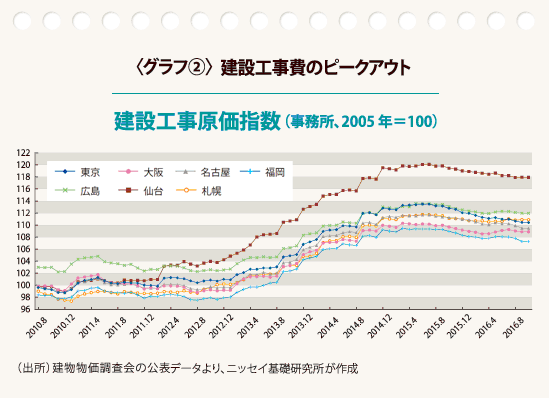
とはいえ、一度上がった賃金を下げれば、再び人材確保が難しくなるのは目に見えているので、今後、建設工事費の全体的な水準が劇的に下がる、といったことは考えにくいかもしれません。ただ、東北の復興事業や東京五輪関連のほか全国的な公共事業に伴う建設需要も少しずつ落ち着いていく見通しですので、少しずつ下がっていくことはあっても、これまでのように右肩上がりの高騰が続いて建設工事費がさらに上昇していくことはまずないと思われます。


Let’s Plaza(年3回発刊)では、
- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集
- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向
- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー
などの内容を取り上げています。
皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、
ぜひお役立てください。




