納税方法を考える
相続税の納税方法は、言うまでもなく現金による一括納付が原則です。ただ、現実問題として現金が相続財産の大半ということも少ないでしょう。従って、金銭納付が困難な場合に備えて、延納や物納という納税方法が用意されています。
金銭での納付が困難な場合といいましたが、それは相続財産に金融資産が少ないというだけではありません。相続人が持っている固有の金融資産までもがその対象となるため、それをも考慮して、納税が困難かどうかを判定するのです。
しかも、これらの判定は相続人ごとにおこなうことになります。そのため、相続人のうち、長男は延納が認められても、二男は認められないという事態も生じます。
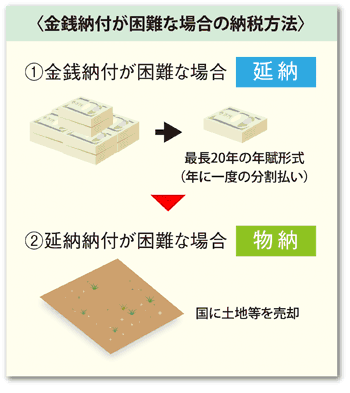
そこで、まずはじめに延納ですが、これは最長で20年の年賦形式、つまり年に一度の分割払いです。金利は相続財産の不動産等の割合によって、細かな分類がなされています。 原則的な利率が定められていますが、特例で実際には“国内銀行の貸出約定平均金利”といわれる金利に連動することになっています。従って、延納をする際には、金融機関からの借入れと比較して判断をすればよいでしょう。
ただし、住宅ローンのように元金と利息の合計額が毎回同額になる元利均等払いではありません。元金の返済額が常に一定の元金均等払いです。そのため、返済当初の数年は元金の他に多額の利子が加わり、負担感は重いものとなるでしょう。
もうひとつの納税方法は物納です。物納とは国にその土地等を売却することですが、この場合には譲渡税はかかりません。また、財産の引き取り価額は相続税の評価額そのものです。
売却ならば、売却価格から先に述べた譲渡税と仲介手数料等の諸経費を控除した金額。一方、物納ならその財産の相続税評価額。従って、売却と物納とどちらが有利か不利かは売却価格のみならず、手残り額で判断する必要があります。この損得勘定はそれ程難しい計算ではありませんので、すぐに判断はできます。
しかし、もし物納が有利となれば、かなりの注意が必要になります。というのは、実際に相続を迎え納税資金を考えて、その段階で売却か物納かの判断をしていたのでは、実務的には遅過ぎるのです。現在の物納制度では、事前の準備が相当程度必要だからです。
物納に必要な事前準備
古い話で恐縮ですが、かつて物納と言えば申請から許可が出るまで時間がかかることで有名でした。そのため、実際には物納するつもりもないのに、時間稼ぎのためだけに、物納の申請をすることも多かったのです。
しかし、平成18年度の税制改正で、物納制度は大きく変わり、申請から許可・却下まで、原則的には3か月で結論が出てしまいます。
また、それに伴って、物納の申請時に原則的にはすべての関係書類が整っていることが必要になったのです。
つまり、物納の申請期限でもある相続税の申告期限までに、すべての書類が準備できていなければならず、実際の相続が開始されてから用意していたのでは、とても間に合わないという状況なのです。
なお、注意すべきは現金の一括納付ができない場合、いきなり物納を選択できるわけではないということです。まずは延納によって納税できる限りの金額を算出します。それでも納税ができない場合、そのできない部分についてだけ物納が認められることになるのです。
財産の分割と納税方法はセットで考える
前述のとおり、延納や物納をする場合、それは相続人ごとの判定となります。従って、財産分けをおこなう場合、相続した財産で各人がどれ位の相続税額になるのか、その税額をどのような方法で納税ができるのか、それは相続人それぞれが事前に確認しておくことが必要になります。つまり、財産分けと納税方法の確認は、必ずセットで考えるべきなのです。
例えば、賃貸マンションを相続した場合、そこから上がる収益は納税の原資となります。従って、相続人としては物納を考えていても、税務署はその収益に着目し、延納での納税を要請されることにもなり得るのです。
逆に言えば、物納を選択したいのであれば、現預金はもとより収益性の良い財産を相続してはいけないということなのです。典型的な例として、借地人のいる底地を物納財産にあてたいのであれば、底地を特定の相続人に集中して相続させるのです。底地は不良資産の代表例ですが、収益性も低く物納にあてる財産としては最適かもしれません。
また、冒頭の取得費加算の特例ですが、今後は従来より確実に譲渡税の負担が重くなります。しかし、それでも適用できるのであれば、適用した方が有利です。
例えば、配偶者が相続した財産については、一定額までであれば特例の適用で相続税の負担はありません。つまり、配偶者が売却予定の土地等を相続しても、相続税の納税自体がないため、取得費加算の特例が適用できないということもあるのです。
取得費加算の特例の改正を契機に、納税対策を今一度考えてみることは、有用なことなのではないでしょうか。
※本記事は2014年6月号に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。

税理士。昭和27年生まれ。早稲田大学教育学部卒。税理士法人エーティーオー財産相談室代表社員。国税専門官として税務調査を10年強経験後アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。経験を生かした資産税のスペシャリストとして活躍中。著書に『相続に強い税理士になるための教科書』『相続財産は法人化で残しなさい』『円満な相続の本』など。
税理士法人ATO財産相談室
阿藤芳明 コラム一覧


Let’s Plaza(年3回発刊)では、
- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集
- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向
- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー
などの内容を取り上げています。
皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、
ぜひお役立てください。



