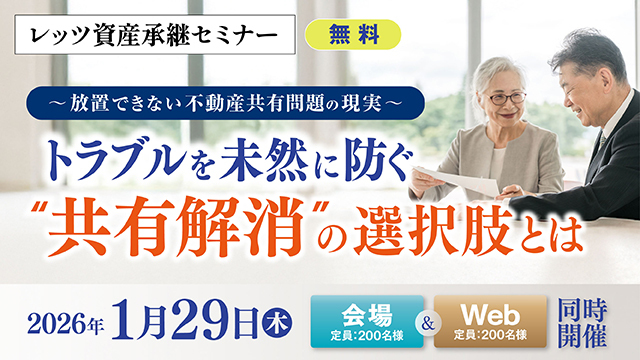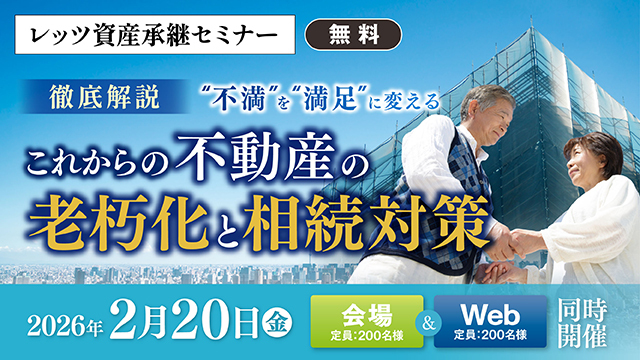〈今回のテーマ〉子世代が困る債権・債務の相続を考える
父が亡くなり、相続人は長男と次男の私と長女の3人です。遺産分割協議で父の遺産のうち、アパートとその建築時に銀行から借りた借入金を長男が相続することになりました。このアパートの借家人の1人が多額の家賃を滞納しているのですが、父が存命していた時期の滞納家賃の請求権も、アパートの所有者の権利だと兄が主張しています。長男の主張は正しいのでしょうか? さらに、長男が銀行への返済金を滞納したところ、銀行から私と長女に支払い請求がありました。私や長女が銀行に請求されるいわれはあるのでしょうか?
金銭債権は相続人の法定相続分に従って分割される
滞納家賃の支払い請求権や、売買代金の請求権など、分割して給付を求めることができる債権を「可分債権」といいます。アパートの滞納家賃であれば、アパートを取得した者が滞納家賃債権も相続するように思えますが、法律上、滞納家賃債権はアパートとは別の財産権です。滞納家賃のような金銭債権は可分債権ですから、遺産分割の対象財産ではなく、当然分割財産と法律で定められています。
「当然分割」とは、相続開始と同時に当然に相続人の法定相続分に従って分割が完了する財産のことです。つまり、滞納家賃は、相続開始と同時に相続人の法定相続分に従って分割が完了しているのです。もっとも相続人の全員一致で滞納家賃の取得者を遺産分割協議で決定することも法律は認めています。そのため、ご質問のように相続人同士でもめてしまうことがあるわけです。こうしたことにならないよう、被相続人となる方は、金銭債権は誰が取得するかを遺言などで決めておくようにしましょう。
金銭債務も法定相続分に応じて請求されることがある
アパート建築などで生じた借入金は、アパートの家賃から返済するのが通常なため、アパートを相続した者が借入金も相続すると思う方は少なくないと思います。しかし、金銭債権と同様の考え方で、金銭債務も分割して給付することが可能ですから、法律上は可分債務であり、遺産分割の対象財産ではなく、当然分割財産とされています。
もちろん相続人全員が合意すれば、アパートを取得する相続人が借入金も相続する、つまり債務者を相続人の1人にすることは可能です。しかし、債権者である銀行からすると債務者を勝手に変更されては困りますので、法律上、債務者を相続人の1人にすることを決めた分割協議書は債権者には対抗できません。従って、ご質問のように長男が銀行に対する返済金を滞納すると、債権者である銀行は本則に従い、各相続人に対し相続分に応じて借入金の支払いを請求することがあり得ます。
こうした事態を防ぐ方法としては以下の2つが考えられます。1つは、長男1人を債務者とし、他の相続人が相続分に応じて承継した借金を免責してもらう「免責的債務引受契約」を債権者と相続人全員との間で成立させることです。もう1つは、相続の放棄です。長男以外の相続人が相続の放棄をした場合は相続人ではなかったものとみなされ、可分債務である借入金を承継することはありません。
そうお話すると、遺産分割協議書を示し「私は被相続人の遺産を受け取っていません。相続を放棄しているから大丈夫です」と言う方がいらっしゃいます。しかし、この方は「相続の放棄」ではなく「遺産の放棄」をしたに過ぎないため、借入金の請求を受ける可能性があります。相続の放棄とは、自己が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し受理されることをいいます。また、相続の放棄をした場合は、借入金などの債務だけではなく、全財産を引き継げなくなります。相続放棄と遺産の放棄は違うことに留意しましょう。
被相続人の方は、相続財産に可分債権や可分債務がある場合はこれまで述べてきた点に留意し、あらかじめ相続人とよく話し合っておくことが望ましいと思います。

東京大学法学部卒業。弁護士(東京弁護士会所属)。最高裁判所司法研修所弁護教官室所付、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員、民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長、NHK文化センター専任講師、不動産流通促進協議会講師、東京商工会議所講師等を歴任。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事。
海谷・江口・池田法律事務所
江口正夫 コラム一覧
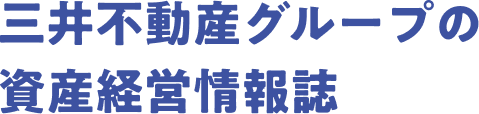
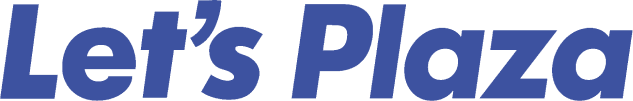
Let’s Plaza(年3回発刊)では、
- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集
- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向
- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー
などの内容を取り上げています。
皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、
ぜひお役立てください。