使い勝手がよいのは「所有型法人」
法人を活用する場合は、より多くの賃貸収入を子などの親族に移転できたほうが税負担の軽減が図れ、法人の運営方法も広がります。そのためには、所有型法人の活用を考えるのが大事です。具体的には、賃貸建物を建築するのであれば、金融機関からの融資も法人で受けて建てる、あるいは購入することになります。また、既存の個人所有の賃貸建物については、時価で法人へ売却すればよいのです。
では、時価はどのように考えればよいのでしょうか。固定資産税評価額を参考にするのも1つの方法ですが、実務的には確定申告書に記載されている未償却残高、いわゆる帳簿価額相当で建物を売却すればよいでしょう。帳簿価額による売却ですから、売主である個人に譲渡所得税の負担は生じません。ただし、賃貸建物の売却は消費税の課税売上に該当しますので、消費税への影響は別途考えておく必要があります。なお、区分所有マンションの場合は建物だけの売買はできず取引相場もあります。そのため、単純に帳簿価額を用いることはできませんので検討が必要です。
また、土地は個人所有のままで、建物を法人所有にする場合には若干の注意が必要です。法人の立場からすると、身内とはいえ他人の土地に建物が建っていることになります。この場合、法人には借地借家法上の借地権が生じるため、土地所有者が権利金を収受する慣行があるにもかかわらず収受しないときは法人へ借地権を贈与したとみなされ、法人税が課税されます。回避するためには、特別な手続きを踏む必要性があります。
詳細な説明は省略しますが、通常は「土地の無償返還に関する届出書」を税務署へ提出することで、課税問題をクリアします。そして、この場合の土地の相続税評価額は更地(自用地)評価額の8割になり、賃貸建物が個人所有のときの敷地(貸家建付地)評価額と比べても基本的に不利益は生じない設定となります。
前述の通り、土地の相続税評価額は更地評価額の8割になるため、相続時には土地評価額の2割相当が借地権として、建物を所有する法人の財産に計上されます。したがって、法人の株価を計算する際には、借地権相当分が株価の上昇要因となり、被相続人が株主の場合は相続財産が増えることとなってしまいます。その意味では、被相続人が株主でなければこの影響を受けることがありませんので、法人の出資者、株主は子や孫にしておいたほうがよいと言えます。
相続開始時期によって「所得型法人」が不利な場合も
また、所有型法人の活用は、相続開始の時期によっては相続税対策上、不利になることがあるため注意が必要です。個人で建物を建築すれば、建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基に計算されます。この固定資産税評価額は、実際の建築額より低い価額になることから、個人はこの評価差額を享受することができます。
子が株主の法人で建築した場合には、評価差額のメリットは法人の株価には影響したとしても、相続税には反映されません。ただし、相続開始時までの収益を法人へ移転することができます。つまり、相続までの期間が短いのであれば個人で建築したほうがよいかも知れないということです。この場合には「管理型」か「サブリース型」の法人活用を行いましょう。逆に相続まである程度の期間がある方は、「所有型」の法人活用をしたほうが最終的には有利になります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、法人を上手に活用した賃貸経営を行いましょう。

税理士。1978年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。2005年、税理士法人エーティーオー財産相談室入社。資産税を中心とする税務申告、不動産税務コンサルティング業務などを提供。2021年、同法人代表社員に就任し、現在に至る。著書に『土地の有効活用と相続・承継対策』(税務研究会出版局)など。
税理士法人エーティーオー 財産相談室 代表社員
高木 康裕
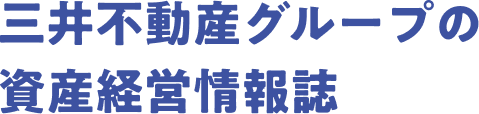
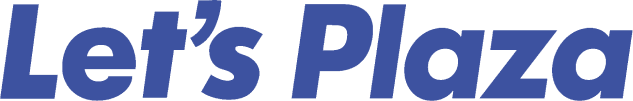
Let’s Plaza(年3回発刊)では、
- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集
- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向
- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー
などの内容を取り上げています。
皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、
ぜひお役立てください。



